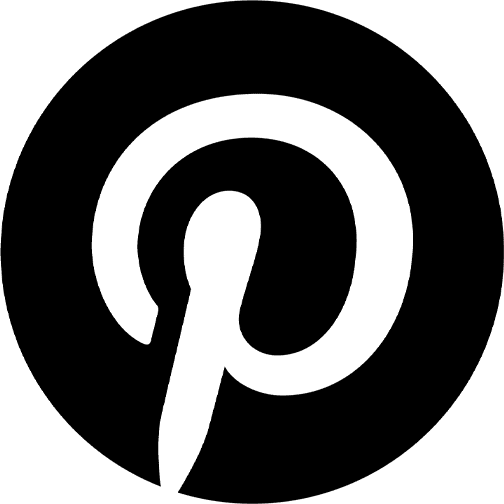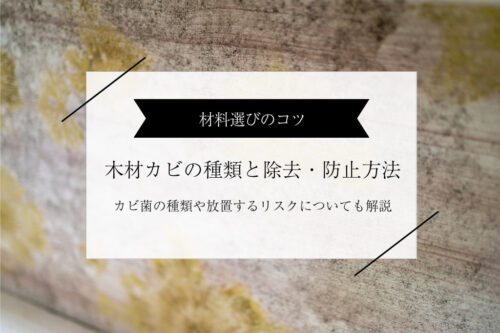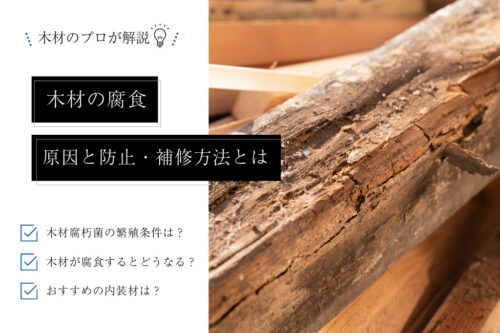“地産地消”でSDGsに貢献|メリット・デメリットと具体例を徹底解説

様々な分野でSDGs実現に向けた取り組みが行われていますが、その中でも重要なキーワードとして注目されているのが「地産地消(ちさんちしょう)」です。
地産地消と聞くと農作物や水産物をイメージしますが、実はその他のものでも導入されています。
そこで今回は、「地産地消」について、取り組むメリットやSDGsとの関連性、具体例、デメリット・注意点について詳しく解説します。
“恩加島木材”が自信を持って提案する、国産木材を用いた内装建材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。
● 森林大国である日本において、建築における木材の地産地消は、大きなCO2削減効果につながり建物の価値を高められます。
● 恩加島木材は1947年創業以来培ったネットワークを駆使して、国外だけではなく国内各地から良質な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造販売しております。
Contents
地産地消とは|取り組むメリット

地産地消とは、国内の地域内で生産・加工されたものを、同じ地域内で消費する取り組みを指します。
【地域資源の活用】+【生産者と地域企業の連携】+【消費者への普及活動】=【地産地消】
郊外や観光地でよく見かける直売所などは、まさに地産地消の象徴的場所です。
農林水産省では地産地消の対象を「農林水産物(食用に供されるものに限る)」としていますが、SDGsの実現や脱炭素化に向けて、そのほかの分野でも地産地消への移行が活発になっています。
(参考:農林水産省|地産地消(地域の農林水産物の利用)の推進)
地産地消に取り組むメリットは以下の通りです。
消費者の安全性・安心感アップ
その地域で製造・加工されたものは、生産者の“顔”が見える点が大きなメリットです。
消費者自らで生産状況や管理状況を確認できるため、衣食住の安心安全につながります。
生産者にとっても消費者との距離が近いため、リアルなニーズや評価を事業に取り入れやすい点もポイントです。
地方経済の活性化・雇用確保
東京一極集中が顕著な日本において地方創生は大きな課題ですが、地産地消はその解決にもつながります。
林業・農業・漁業やそれに付随する生産業の収益性が高まると、地域に雇用を生み出して地方経済を活性化できるためです。
また、生産者と消費者の距離が近いため、流通や仲介業者の中間マージンなど原価以外にかかる経費を削減できて、リーズナブルな価格と生産者の手取り増加の両方を実現できる点も重要なポイントです。
実際に、直販所などでは規格外品・不揃い品などを販売して収益性を高めている生産者は少なくありません。
実際に、地産地消で成功している地域では、林業・農産業・漁業の6次産業※化が進んでいます。
※6次産業:1次産業従事者が地域の資源を活用し、自らで加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)を行う多角的な経営スタイル
環境負荷の軽減
地産地消は、生産物の輸送距離を短縮できるため、省エネやCO2排出量削減をもたらします。
国土交通省の調べによると、日本のCO2総排出量(9億8,900万トン)のうち、運輸部門にかかわる排出量は約20%(1億9,014万トン)を占めることから、地産地消による削減効果は決して少なくありません。
地域の文化継承
その地域に古くから伝わる産業は、”文化そのもの”です。
林業・農産業・漁業などの繁栄を祈るお祭りが数百年も続いている地域は珍しくありません。
また、地元の生産者と消費者が交流することで、文化の理解を深め、地域への愛着を育む側面もあることから、地方回帰促進の取り組みとして地産地消を進める自治体も増えています。
田畑・森林などの荒廃防止
田畑や森林は、放置されると徐々に荒廃します。
実際に、全国各地で従事者の高齢化や人手不足によって耕作放置地や放置林・所有者不明林の増加が進んでいるのが現状です。
耕作放置地や放置林・所有者不明林が増加すると、地滑りなどの自然災害が増えたり、病害虫・野生動物の繁殖や不法投棄、火災リスクの増加につながります。
(参考:農林水産省|農地・耕作放置地面積の推移、林野庁|森林・林業・木材産業の現状と課題)
▶︎おすすめコラム:
なぜ“放置林”が増加している?原因と解決策・活用方法を解説
国内自給率のアップ
日本の食品自給率は、1965年(86%)から2023年(61%)までで25ポイントも減少しており、木材自給率も40%台をキープしているのが現状です。
(参考:農林水産省|日本の食料自給率、林野庁|「令和5年木材需給表」の公表について)
国内自給率が低い状態では、気候変動や関税変動の影響が大きく、消費者の生活に直接影響を及ぼすリスクがあります。
そのため、政府は様々な分野で地産地消を推進し、国内自給率アップを目指しているのです。
▶︎おすすめコラム:
日本の木材自給率はどれくらい?国の取り組みからウッドショック・世界情勢との関係まで詳しく解説
そのため、持続可能な社会実現に向けた重要な課題として、各地域が地産地消の推進に取り組んでいます。
地産地消とSDGsの関連性|該当する目標は何番?

地産地消とSDGsの関わりは深く、いくつもの開発目標において達成をもたらすとされています。
8番「働きがいも、経済成長も」
- 地域の状況に応じて、そこで住む人々が経済的に豊かになるように取り組み、結果的に国内総生産(GDP)の成長につなげる
- 商品の価値を高めるために、技術の向上を通じて生産性を高める
- 地域に働きがいのある仕事を増やし、行政や大企業は中小企業・個人事業主の成長をサポートする
- 2030年までに、地域がより効率的に資源を有効活用し経済成長を遂げられるようにする
- 地方の文化や特産品を広め、持続可能な観光業を実現させる
▶︎地産地消によって都市部以外にも雇用を生み出し、経済成長を実現させる
9番「産業と技術革新の基盤をつくろう」
- 2030年までに地域の状況に応じて、資源を無駄なく活用する
- 2030年までに環境に優しい生産技術を取り入れて、インフラ・産業の持続可能性を高める
- 地域産業の発展に伴い、価値ある商品を生み出し、行政は技術開発や研究・イノベーションをサポートする
▶︎その地域独自の商品・サービスを開発し、地産地消によって廃棄品やコスト面でのロスを減らして資源をフル活用する
12番「つくる責任、つかう責任」
- 天然資源を持続的に管理しながら使用し、効率性を高める
- 2030年までに、生産者・消費者が廃棄する食料を半分に減らす
- 2030年までにゴミの排出を減らし、リサイクル・リユースを促進する
- 国際的なルールに則り、化学物質や廃棄物などの排出量を管理できるようにする
- 人の健康や自然環境に与える悪影響を最小限に減らして、大気・水・土壌の汚染を食い止める
▶︎地産地消によって品質的に問題のない廃棄物を減らす
13番「気候変動に具体的な対策を」
- 自然災害が発生した際に、地域が速やかに立ち直れる“力”を備える
- 気候変動が起きるスピードを緩めるために、省エネ・CO2削減に努める
▶︎地産地消によって田畑や森林の荒廃を防いで自然災害のリスクを抑え、さらに運輸によるエネルギー消費・CO2排出を削減する
14番「海の豊かさを守ろう」
- 2025年までに海洋ゴミや富栄養化※などの汚染原因を減らす
- 水産資源ごとの特徴をとらえ、その種の全体数を減らさず、計画的な漁業を実施する
- 漁業や水産物加工によって、観光によって経済的な利益を得られるようにする
※富栄養化:湖・沼・海・河川に窒素やリンなどの栄養塩が過剰に流れ出て水中の植物プランクトンが過剰繁殖する現象。プランクトンの増殖によって、酸素が足りず魚介類が死滅する環境問題につながる。
▶︎漁業者と水産加工者が同一、もしくは距離が近いことで材料ロスを防止でき、さらに地産地消によって収益性を高められる
15番「陸の豊かさを守ろう」
- 国際的なルールに則って、森林・山地などに形成されている陸上生態系や淡水生態系の持続可能性を高める
- 森林の持続可能な管理体制を整えて、森林減少を食い止める
- 衰退した森林を回復させて、植林量を増やす
- 森林保護や再植林など、持続可能な森林運営を進めるために、行政・企業が資金面でサポートする
▶︎地産地消によって農業・林業・木材加工業が収益を得られて、田畑や森林の荒廃・減少を食い止められる
ただし、現実的にはいくつものデメリットや課題を抱えており、実現化していない現状もあります。
地産地消のデメリットと課題

地産地消は、生産者・消費者・行政それぞれにメリットがある取り組みではあるものの、各地で実施する上で見えてきたデメリットや課題も無視できません。
【生産者の抱える悩み】
- 情報交換や情報発信(消費者とのマッチング)の方法が分からない
- 販売ルートを確保できない
- 営業活動に時間を費やせない
- 消費者への直接販売は、代金決済において不安がある
【消費者の抱える悩み】
- 品目数・数量が不安定(出荷量が一定ではない)
- 品目数が少ない
- 規格(品質やサイズ)が不揃い
- 購入ルートが分からない
- 必ずしもコスト面で有利とは限らない
【行政の抱える悩み】
- 地産地消の普及啓発がなかなか進まない
- 独自性を出せない自治体も多い
- 補助金の支給など資金力が必要
(参考:農林水産省|地産地消の現状と課題)
これらの課題を解決すべく、官民で協力し、「地産地消の魅力発信」や、「地域のDX※化」、「各種補助金の支給」などが取り組まれています。
※DX:デジタルトランスフォーメーションの略称で、デジタル技術を用いて業務効率や競争力、生産・サービスの品質を高める取り組みを指し、IT化とは異なり組織全体の変革を意味する。
▶︎おすすめコラム:
森林保全とは?取り組み例と“できること”、保護との違い、関連する税金、おすすめ内装材を紹介
地産地消の具体例|食品以外も

地産地消と聞くと食品をイメージしますが、全国各地ではそれ以外の分野にも地域の資源を生かした取り組みが行われています。
食品(農産物・水産物)
- 直売所や道の駅で生産者自らが商品を販売する
- 学校給食に地元で作られた食材を使い、食育に繋げる
- スーパーマーケットや食品加工メーカーで地元の食材を加工・商品化して、周辺地域に魅力をアピールする
- 自治体が地元食材を使った料理教室を開催し、地域の魅力と文化を発信する
- 旅館やホテルで地元食材を使ったメニューを提供する
- 福祉施設(高齢者施設)や医療施設で地元食材を食事に取り入れる
(参考:農林水産省|地産地消の具体的な取組例)
古紙の再利用
行政や企業でデジタル化が進み不要になった紙の文書は少なくありません。
それらを利用して再生紙を作る取り組みが各地で進んでいます。
- 店舗やオフィスで発生したミスコピーなどを地元の製紙工場で再生紙に加工する
- 再生紙を土産品や特産物の箱に利用し、SDGsへの取り組みを地域外や国外にアピールする
- 印刷会社やデザイン事業者から発生した余剰紙や紙の帳簿・文書を集めて、地元の製紙工場で再生紙へ加工し、エコ商品として売り出す
電力エネルギー
過去の大震災や台風被害によって、集中型のエネルギーシステムの脆弱性が明らかになり、防災的な観点からもエネルギーの地産地消(地域分散型エネルギーシステム)を導入する地域が増えています。
- 商業用風力発電の導入
- 雪氷エネルギーの冷房利用
- 森林資源を活用したバイオマスエネルギーの利用
- 家畜の排せつ物を活用したバイオマスエネルギーの利用
- 学校・プールへの地中熱エネルギー利用
- 砂防ダムの未利用水源を利用した小水力発電
- 農業用水を利用した小水力発電
木材(地域材・地産材)
日本はその国土の2/3を森林が占める世界でも数少ない森林大国です。
その特長を生かし、地域で育った木材(地域材・地産材)の活用が進められています。
- 地域材・地産材を土産品や工芸品の材料として利用
- 地域材・地産材を建築材料(構造材・内外装材)として利用
- 地域材・地産材を用いた建築プロジェクトに補助金を支給する
(例:大阪府|令和7年度民間施設における木質空間整備事業補助金)
▶︎おすすめコラム:
今こそ木材も“地産地消”する時代。脱炭素化に向けた地産材・地域材利用について解説
国産材が使われない6つの理由。建築が木材自給率アップのためにできることは?
国産材を用いた場合と比べると、運輸で発生するCO2排出量は、北米産木材の約1/5、ヨーロッパ産木材の約1/9程度です。
そのため、脱炭素化を目的に建築における地産地消の動きが活発化しています。
地域材・地産材を利用した恩加島木材の「突板化粧板」

「突板化粧板」とは、表面に天然木を薄くスライスした突板を用いたパネル材で、家具や内装建具の表面材、壁・天井の仕上げ材など幅広く採用されています。
▶︎おすすめコラム:
天然木にこだわるなら突板練付化粧板。メラミン化粧板・オレフィン化粧板・プリント化粧板との違いは?
突板・挽板・無垢材それぞれの違いとは?どれがおすすめ?特性から選び方まで徹底解説
恩加島木材は、海外からだけではなく国内各地から良質な突板を仕入れ、高品質な突板化粧板を製造する建材メーカーです。
【地域材・地産材の納入実績例】
・JR北陸新幹線・長野駅 コンコース内天井(長野県産杉利用)
・香川県多度津町庁舎(香川県産材利用)
・某百貨店 什器(大阪府内産桧利用)
・新居浜商業高校 体育館(愛媛県産材利用)
・京都女子大学(京都府内産桧利用)
・京都 某ホテル(京都府内産利用)
その他の地域材に関するご要望も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
恩加島木材が自信を持って提供する「突板化粧板の強み」は以下の点です。
- 無垢材と同様の「ナチュラルな見た目と質感」に仕上がる。
- 工業製品なので「品質安定性が高い」。
- 軽量化を実現でき、「施工効率性アップ」につながる。
- 無垢材よりも温度や湿度環境変化による「変形リスクが少ない」。
- 希少性があり高価な樹種でも、「無垢材より安価」で安定して材料を入手しやすい。
- 原木1本から取れる突板面積は無垢板材よりも広いため、「同じ風合いを大量入手しやすい」。
- 特殊塗装によって「表面の耐摩耗性・耐汚性」が高く、日焼けによる変色も抑えられる。
- 「不燃・難燃材料認定取得済み」製品もあり、内装制限のある建築物にも採用可能で、対象部分と対象外部分の仕上げを揃えられる。
さらに弊社では、間伐材、成長の早い小径材を積極的に活用し、森林活性やカーボンニュートラル実現に向けた取り組みも行っています。
● 重い・割れやすい・高コスト・ビスが効かないなどの懸念点を解消した「不燃突板複合板」
● 国内初・組み立てた状態で準不燃認定を取得した「リブパネル」
● 国内初・孔を開けた状態で不燃認定を取得した「有孔ボード」
● 0.5mm厚突板による立体感と特殊UV塗装で耐久性と抗菌性能を付与した日本初上陸のプロダクト「突板化粧合板・KDパネル」
内装制限の対象となる建築物へご採用いただける製品を取り揃えておりますので、建物の設計デザインに木目を取り入れたい方はお気軽に弊社までご相談ください。
▶︎おすすめコラム:
突板製品はこうして生まれる。森から現場までのプロセスは?生産工程や恩加島木材の強みを紹介
まとめ
地産地消は様々な分野で取り組まれており、SDGsの開発目標とも深く関わります。
森林大国である日本において、建築における木材の地産地消は、大きなCO2削減効果につながり、建物の価値を高める点もポイントです。
恩加島木材では、人の生活環境と地球環境の両方に配慮した高品質な突板化粧板を製造しております。
地域材・地産材利用のご相談も承っておりますので、「思い通りのデザインを実現したい」「環境に配慮した建物にしたい」という方は、レパートリー豊富な恩加島木材の突板製品をぜひご採用ください。